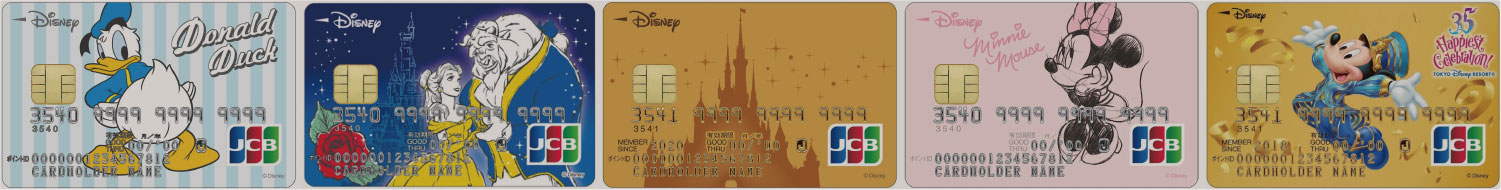①全面リニューアルによる、新たなミュージカルショー「キング・
トリトン
のコンサート」。
②ダイナミックなパフォーマンスで映画さながらの美しい海底の世界を表現。
③ステージや照明など、これまでの舞台装置が一新。
④客席の周囲に映像を映し出すスクリーンも新たに登場。
⑤
アリエル
が360度泳ぎ回り、ゲストの近くまでやってきて、躍動感あふれる新感覚のミュージカルショー。
①東京ディズニーランドの「ガジェットのゴーコースター」と同様に、車体が通常より小さく、細かい動きが多い。
②速度は33㎞/hでかなり遅めだが、急旋回やアップダウンが多い。
①ゲストが座る椅子は、貝殻の形。
①ブローフィッシュとは、日本語で「フグ」のこと。
①中央のハンドルを回して速度が変わる一般的なコーヒーカップとは違い、遠心力で回るので、座る位置によって動きが変わる。
②2人で向い合せで座ると、重心が安定して回転がゆっくりになり、一ヶ所に固まって座ると、重心がかたより遠心力が増し回転が速くなる。
③乗り物は8の字を描くように回転する。
④水面に浮く海藻をイメージしているアトラクションなので、水面の演出をするため、一ヶ所フワッと浮く場所がある。
①9つのエリアで構成されている。
②「フィッシャーマンズ・ネット」:海の上から下ろされた漁師の網を模した巨大ネット。
・「ケルプ・フォレスト」:巨大な海藻(ケルプ)でできた森。
・「マーメイド・シースプレー」:イルカやカメの像からランダムに水が噴き出し、地面はやわらかいスポンジ状になっている。
・「
アリエル
のグロット」:グロットとは洞窟のことで、
アリエル
の住居という設定。
・「シー
ドラゴン
」:シー
ドラゴン
の骸骨でできたトンネルで、
アースラ
のダンジョンへ続いている。
・「ケープ・オブ・シャドー」:白い壁の洞窟で、ときどき閃光を伴った稲妻が走る。
・「ガリオン・グレイヴヤード」:内部に入れる沈没船。
・「
アースラ
のダンジョン」:
アースラ
の棲む洞窟。
・「スターフィッシュ・プレイペン」:全体がヒトデの形の小さなプレイグラウンド。
②プレイグラウンドの遊び方が書かれた「探検マップ」をキャストに頼むをもらえる。
③天井を見上げるとボートが浮いていて、海の中だからこその眺め体感できる。
④「ケープ・オブ・シャドー」のエリアで、壁に体の一部を触れていると、稲妻が光った時に、体の跡が数秒間壁に残る仕掛けがある。
バックグラウンドストーリー
ここは、
アリエル
にとって思い出の場所ばかり。
自分のお気に入りの場所に、人間であるみんなが訪れるのをとても楽しみに待っている。
センター・オブ・ジ・アース
2001/9/4~
地底走行車に乗って神秘に満ちた地底の世界を探検するジェットコースター
TDS
ミステリアスアイランド
①フランスの小説家ジュール・ベルヌの代表作『地底旅行』を原作とし、1959年にヘンリー・レヴィンによって製作された映画をモチーフにしている。
②初めはゆっくり進むが、ライド終盤にはスピードをつけ急上昇、急降下をし、その最高速度は時速75㎞に達する。
③東京ディズニーリゾートのアトラクションの中では最速。
④ライドの原動力は、従来のコースターライドのようにリフトコンベヤーで引っ張られ、その後重力に従って旋回や落下を繰り返すというものではなく、ライドとコースにコンピュータが備え付けられており、コンピュータでライドのスピードや、ライド同士の間隔を調整している。
⑤ライドには、フォーミュラ1のレースカー並の動力を持つモーターを搭載し、その動力によって、加速や減速を行っている。
もっとひみつを見る
⑦2010年の定期点検にて、乗り場へホームドアが設置された。
⑧アトラクションが定期メンテナンスなどの事情で終日休止している時、テラヴェーター直前までの待ち列を見学する「マグマ・サンクタムツアー」(火山の洞窟ツアー)が開かれることがある。
⑨「マグマ・サンクタムツアー」は公表されているサービスではないため、東京ディズニーリゾート公式サイトや東京ディズニーシー・トゥデイに記載もされていない。
⑩「マグマ・サンクタムツアー」が実施されているかどうかは、アトラクション入口まで行って、キャストに確認する必要がある。
⑪公式サイトでは「センター・オブ・ジ・アース」の名称が使われているが、建物入口の右脇にあるロゴには「Journey to the Center of the Earth(ジャーニー・トゥ・ザ・センター・オブ・ジ・アース)」と正式名称が書かれている。
バックグラウンドストーリー
時は1870年代初期。
謎の天才科学者ネモ船長はミステリアスアイランドの科学研究所で、海底と地底に関する研究を行っている。
火山内部に驚異の地底世界を発見したネモ船長は、世界中の科学者たちをこの場所に招待し、研究の成果を披露している。
ゲストは世界中から招かれた科学者。
ネモ船長が発明した地底走行車に乗り込み、神秘的で美しい地底世界を見学することがききる。
削岩機によって掘られた通路を進んで行くと、ネモ船長の研究室や彼のクルーが研究を行っている生物研究室があり、ここでしか見ることのできない貴重な道具や参考資料、標本などがある。
奥へ進むと、地底走行車の乗り場へ向かう「テラベヴェーター」が設置。
「テラベヴェーター」はネモ船長が発明したエレベーターで、地下800m地点とつながっている。
「テラベヴェーター」内には様々な計器があり、深度や二酸化炭素濃度、蒸気圧を表示。
いよいよ地底走行車に乗り込む。
6に乗りのヴィークルは、岩石などを押し分けながら走行できるように、前部はブルドーザーのようになっている。
後部には動力である高圧蒸気のタンクがある。
さあ、神秘的で美しい地底世界の見学へ出発!
海底2万マイル
2001/9/4~
小型潜水艇に乗り込み海底の世界を探検する
TDS
ミステリアスアイランド
①フランスの小説家ジュール・ベルヌが1870年に発表した小説『海底二万里』と、この小説を原作として1945年にリチャード・フライシャーによって製作された映画『海底二万哩』をモチーフとしている。
②ライドは実際水の中には入らないが、ライドの窓に映る泡や、振動で実際に水の中にいるような演出がなされている。
③窓の上部に、潜行深度と潜水艇内の酸素濃度を示すメーターが取り付けられており、これは物語の進行と連動しており、最後ライドを降りる時には残りの酸素が少なくなっている。
④アトラクションの名前の意味は、「海の深さが2万マイル」ではなく、ネモ船長が開発した潜水艦ノーチラス号が「海底を2万マイル旅した」という意味。
⑤1マイル約1.6㎞なので、2万マイルは約3万2千㎞。
もっとひみつを見る
⑦待ち列では、映画『海底二万哩』に登場する小道具や、貴重なネモ船長の肖像画を見ることが出来る。
⑧キャストは「ネモ船長の部下」という設定であり、海底探索の研究員であり乗組員でもあるので、「クルー」と呼ばれる。
⑨クルー同士のあいさつも他のキャストとは異なり、「モビリス」という言葉に「モビリ」と返答する。
⑩「モビリス・イン・モビリ」という「変化をもって変化する」という、アトラクションの原作となっている小説内で使われている言葉。
⑪ミステリアスアイランド内のマンホールにも「MOBILIS IN MOBILI」と書いてある。
バックグラウンドストーリー
謎の天才科学者ネモ船長が開発した小型潜水艇「ネプチューン号」。
これまででは行くことが出来なかった狭い場所も海底探索ができるようになり、神秘に包まれた深海を探索する”志願クルー”を募集。
”志願クルー”はネプチューン号に乗り込み、ネモ船長が実験する海底菜園や、美しい海底を探索。
ネプチューン号は、ネモ船長のいるコントロールベースから遠隔操作がなされており、安全を確保されている、はずだった…。
多くの船が沈没する海域「船の墓場」があり、ここでは沈没する理由は謎に包まれている。
潜水艇を浮上させようとした時、謎の生物「クラーケン」に襲われ、コントロールを失い、誰も訪れたことのない未知の世界へ迷い込んでしまう!
迷い込んだ先では、なんと、海底人の暮らす世界だった。
”志願クルー”の乗ったネプチューン号は無事基地へ帰還することができるのか。
①リキッドシアターと呼ばれ、海の中を再現したもの。
②
アリエル
とその仲間たちが「海の素晴らしさ」を歌うミュージカルショー「アンダー・ザ・シー」。
③舞台中央に円形ステージがあり、360度客席が囲む設計になっているので、どの方向からも楽しめるようになっているが、入口一番奥(宝箱の正面)が一番見やすい。
④天井から宙づるになった役者による「フライング」の演出で、実際に海の中を泳いでいるかの様に感じられる。
⑤ショーの中で
アリエル
が、映画でも使われている「パート・オブ・ユア・ワールド」を歌い上げる。
もっとひみつを見る
⑦2014年4月6日に公演終了し、それに伴って施設リニューアルを行い、2015年4月24日より、新たなエンターテインメントが公開された。